

三ツ股 慧2007年入行
麻生 絹子2020年入行
三ツ股 慧2007年入行
麻生 絹子2020年入行
- TOP
- 【スペシャルコンテンツ】CROSS TALK03 理系 × 理系
「銀行員は文系出身者の仕事」と思っていませんか?大分銀行の場合、それには当てはまりません。近年は理系出身の行員が増えており、重要なポジションを担っています。多様な行員がいるからこそ、地域のニーズに応えるサービスを届けられるのです。



その前に、それぞれの仕事について紹介しましょう。私は総合企画部に所属していて、大分銀行の経営戦略の策定に携わっています。銀行全体の中長期を見据えた経営計画の策定や部課店のごとの人の配置計画、新規事業の検討等、内容は多岐にわたります。策定にあたっては、地域の社会・経済状況、全国の地方銀行の取り組み等を分析し、どうすれば大分銀行の特色や強みを発揮できるかを、さまざまな視点から考えます。ただ考えるだけでは意味がなく、それをステークホルダーに認識してもらい、実行するための方法を検討するのも重要です。
私は所属している個人営業支援部アセットコンサルティング室のスローガン「大分を豊かに」の実現に向けて、お客さまに投資信託や株式投資等に関する資産運用の提案とコンサルティングを行っています。
さて、先ほどふれた当行の「中期経営計画2024」は、基本テーマとして『私たちにしかできない「金融+α」縲怐g挑戦”を“あたり前”に』というフレーズを掲げています。この基本テーマを実現するためには、客観的なデータや事実に基づいて考える論理的思考に加えて水平思考も欠かせないと考えています。課題解決に向けて取り組む際は、論理的思考で必須であるPDCAサイクルをまわすことが有効です。しかしそれだけでは充分ではなく、地域やお客さまのニーズを正確に把握して、金融サービスとして具現化するためには、柔軟な発想につながる水平思考が重要だと思っています。先ほど言ったように、そのあたり麻生さんは得意ですね。
スケールの大きい話になってきましたね(笑)。でも、どんなに大きな計画であっても行員一人ひとりの業務とリンクしていると思います。私の仕事でいえば、より良い提案をするためには、多くの情報のなかから有効なものをピックアップして、それを実際の取り組みに反映させる必要があるので、PDCAサイクルは確実に役立っています。もうひとつ理系の学習で役立っているのが、“鋼のメンタル”(笑)。実験では思い通りの結果がでないことが大半で、そこで諦めることなく試行錯誤を重ねて、少しずつ前進していくことを学びました。そういった姿勢は、コンサルティングを行う上でとても大切です。
本当にその通り。経営戦略でも、設定した目標に向かって正しく進んでいるのか、改善するところはあるのかを常に検討しなければいけません。そのためには客観的なものの捉え方と、諦めずに持続して取り組む力が必要です。


水平思考について自分なりに考えると、日々の業務の質向上や「中期経営計画2024」の実現のためには、大分銀行の状況だけではなく、お客さまの目標や課題はもちろんのこと、地域、市場、さらには国内外の経済等、幅広い領域において数値化できないことをキャッチアップする必要があります。そして、幅広くアンテナを張り、いろんな角度で物事を見て、問題点や新たな可能性を捉えるアプローチが欠かせません。こうした元になる考え方が水平思考なのかなと思います。特に社会・経済がますます多様化するなか、個人・法人のお客さまにかかわらず大切な要素になるでしょう。
経営戦略は、約2,100名の行員、ひいては地域の方々にも影響を与えるものなので責任は重い。結果はデータとして現れるだけでなく、みなさんの声からもわかります。このように、ダイレクトに反応が返ってくる点が怖さであり、同時に魅力でもあります。
銀行といえば、まだまだ文系というイメージが強いかもしれませんが、理系出身者も力を発揮できるので、関心のある人はチャレンジしてほしいです。
最初に話したように、理系・文系にこだわる必要はありません。要は、一人ひとりの仕事に向き合う姿勢が大切ということ。ただ、大分銀行には、理系出身者も活躍でき、さまざまなチャレンジができる環境があることは伝えたいですね。

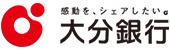













私は理工学部で主に“ものづくり”に関する勉強をしていたのですが、大学卒業後は生まれ育った大分県で働きたいという想いがありました。そして、地域に貢献できる仕事を考えたところ、まず頭に浮かんだのが銀行員だったんです。これまで学んできたこととマッチしないのではないかという不安はありましたが、入行してみるとまったくそんなことはなくて、お客さまとコミュニケーションをはかるきっかけになっています。
私は農学部出身で、お客さまのなかには農業をされている方もいらっしゃり、話がはずむこともあります。就職活動では、私も大分で働くことが前提としてありました。農学部で学んだ知識を仕事で直接活かそうとすると大学院に進んだ方が有利な傾向があり、大学院に進むよりも就職して働きたいと思ったんです。銀行を志望した理由は、三ツ股さんと同じ。大分銀行は県内にたくさん支店があるので、お客さまと近い関係でお役に立てると思いました。金融に関する知識はほとんどありませんでしたが、新しいチャレンジにワクワクしたことを覚えています。
大分銀行の場合、理系出身者は2縲鰀3割程度で、数字的には文系出身者の方が多い。でも、毎日の業務では、誰が文系で、誰が理系かと意識することはありません。
ですよね。お客さまや行員同士の雑談で話題になることがある程度。それを言っちゃうと、このクロストークは終わってしまいますよ(笑)。
私は麻生さんが入行した頃、採用担当だったので、面接にも対応させてもらいました。その時に、いろいろなことに興味をもち、多角的に物事を捉える水平思考ができる人だと感じました。個人的な印象ですが、水平思考が得意な人は文系に多く、論理的思考が得意な人は理系に多いと思っています。そして、大分銀行が策定した「中期経営計画2024」を実現させるためには、水平思考と論理的思考のふたつが重要なので、麻生さんに力を発揮してほしいと考えたんです。少し話の道筋が見えてきましたね。今回は「中期経営計画2024」を例に挙げながら、水平思考と論理的思考について話しましょうか。